舞鶴市出身で、現在は京都市伏見区にて、作家ブランド・ファクトリーブランドのECサイトを運営している田畑と申します。舞鶴サポーターズコミュニティのレポーターとして、京都府内への移住促進事業「京都ローカルワークステイ」の体験記を寄稿します。
大学進学以降は舞鶴から離れていましたが、空き家となった元実家を相続したことをきっかけに、舞鶴に残る親や親戚のことなど、舞鶴との関わりを考え直すようになりました。
第3回「海の京都サポーターズミートアップ」では、元実家を処分・売却するのか、賃貸物件として活用するのか、京都と舞鶴の二拠点生活に活用するのか…まだ答えは出ていない状況ですが、自身が直面している舞鶴の空き家問題について話をさせていただきました。
舞鶴の空き家問題を考えるにあたり、人口推移などの統計や行政の施策など、舞鶴の現在を調べていたのですが、舞鶴でユニークな事業をされている方がいること、移住促進や地域に関係する人口を増やすための様々な事業が展開されていることにも気づかされました。
京都府内への移住促進事業の1つ「京都ローカルワークステイ」は、京都府内の多様な企業と協力し、課題解決型のプロジェクトに取り組みながら、移住や京都での新しい働き方や暮らし方をデザインするプログラム。
自分自身は移住希望者ではないのですが、今後の舞鶴との関わりを考え、舞鶴の経営者の方とも知り合いたいと思い、2024年11月の「京都ローカルワークステイ」では、舞鶴市の縫製会社・福井センイさんのプログラムに参加。2025年2月には各プロジェクト発表イベントにも参加してきました。
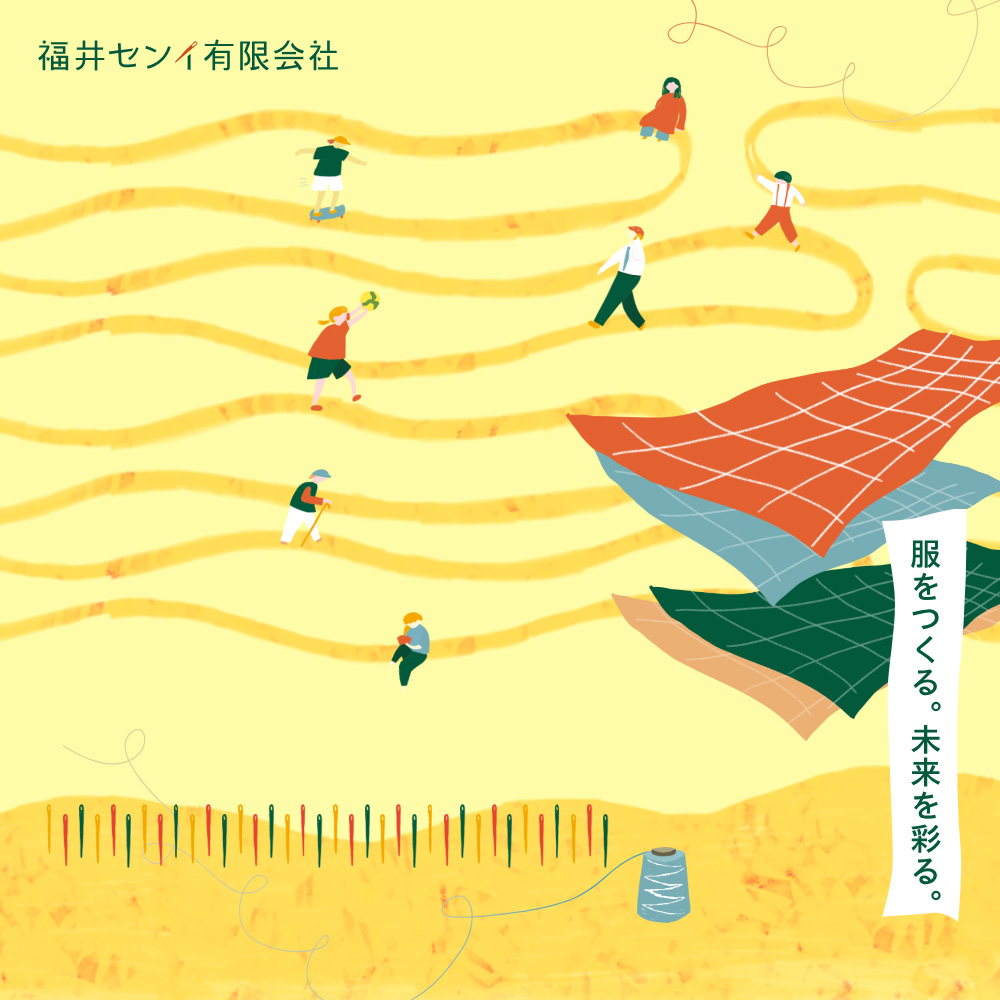

1954年創業の福井センイさんは、西舞鶴の漁港近くの魚屋地区にある縫製工場。福井センイの菅原一輝さんは、千葉県から舞鶴市に移住し、奥さんの実家の家業である福井センイさんに入社。福井センイの3代目として、縫製業の新たな可能性を模索されています。
かつての日本は縫製産業の中心地であり、舞鶴には海軍工廠があったことから、海軍の制服の製造など、繊維産業が盛んでした。近年はファストファッションの台頭により、人件費の安い中国や東南アジア諸国へと生産拠点が移行。現在の日本で流通する衣服の98%程度が海外製となるなか、菅原さんは福井センイさんの縫製業を承継しながら、異分野への進出と融合を図る試みに取り組んでいます。

菅原さんが立ち上げた「SEW」(ソウ)は、従来の縫製の概念を超えたオリジナルブランド。
一般的な「縫製」の概念は、布と布を縫い合わせ、衣服やかばんなどの形にして価値を生み出すことですが、SEWブランドのコンセプトは、布と布の縫製にとどまらず、「都市・人・文化」を縫い合わせ、新しい価値・可能性を生み出すこと。これを「都市縫製」として定義し、縫製業の継承に加え、宿泊施設「SEW STAY」の運営、自社ブランド「SEW FABRIC」の製品開発、福井センイさんの旧工場を改装したイベントスペースの活用など、従来の縫製業の枠を超えた事業を展開されています。


今回の京都ローカルワークステイでは、縫製工場の服づくりの現場見学のほか、「SEW STAY」に宿泊させていただいたり、旧工場ではシルクスクリーンでTシャツ・バッグのプリント体験などもさせていただきました。


また、福井センイさん近くのマナイ商店街やひらのや商店街、海沿いに古い町屋が並ぶ吉原地区を街歩き。
参加者のみんなで行った町中華の「北京」、舞鶴漁港の食堂「水協食堂」は今だからこそわかる魅力があり、大阪出身で舞鶴で水産加工品を手がけるENDEAVOR・松田慎平さんの「ソフト干物」は柔らかな食感と凝縮された魚の旨味が美味しかったです。
また、学生たちが「いつか舞鶴に帰ってきたい」と思えるようなつながりの場「KATALab.」を運営する髙田智哉さんのお話をお聞きするなど、舞鶴の再発見につながる経験になりました。

菅原さんは、福井センイさんの旧工場イベントスペースを起点をした人の流れを生み出すべく、某大手書店と組んで本のイベントを企画中とのこと。
新たなコンセプトをつくり、それを形にしていくのはとても大変なことですが、着実に進めている菅原さんの姿にとても刺激を受けました。
菅原さんの本のイベントもおうかがいして、自分自身の舞鶴との関わり方を含めて、また紹介させていただければと思っています。
